平素はSMILE10デンタルクリニックをご利用いただき誠にありがとうございます。
本年の診療につきましては12月29日(月)まで、新年は1月4日(日)より診療を始めさせていただきます。
12月30日~1月3日は休診となりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
<休診日>
2025年12月30日(火) ~ 2026年1月3日(土)
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
2025年10月15日 カテゴリ:医院からのお知らせ
ホーム > ブログ > efconnect01 スマイル10 矯正歯科・小児歯科 センター北の歯医者/歯科医院
平素はSMILE10デンタルクリニックをご利用いただき誠にありがとうございます。
本年の診療につきましては12月29日(月)まで、新年は1月4日(日)より診療を始めさせていただきます。
12月30日~1月3日は休診となりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
<休診日>
2025年12月30日(火) ~ 2026年1月3日(土)
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
2025年10月15日 カテゴリ:医院からのお知らせ
小児歯科と小児矯正の大切さ「ただ虫歯を治すだけじゃない」未来を守る選択
「子どもの歯医者って、虫歯になったときに行く場所でしょう?」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
でも実際には、子どもの歯科は虫歯を防ぐだけでなく、
「お口全体の機能を正しく発達させる」ために非常に重要な役割を持っています。
歯並びが悪くなる原因は、単なる遺伝や乳歯の並び方だけではありません。
顎や舌、呼吸の仕方(鼻呼吸 vs 口呼吸)、食事の癖、姿勢、指しゃぶりや頬杖といった生活習慣が
複雑に絡み合い、成長期の子どもたちの口腔機能や顔立ち、さらには全身の健康にまで影響を及ぼします。
だからこそスマイル10矯正歯科・小児歯科は、
「虫歯ゼロ」だけで終わらない——子どもの未来のために大切な機能を育む場
として、小児歯科・小児矯正に全力を注いでいます。
なぜ「今」が大事なのか? 成長期は一生に一度しかない
顎や顔面の骨は、実は脳と同じ「神経型」という成長パターンをとり、12歳頃までにほぼ完成します。
このタイミングを逃すと、
さらに口呼吸や舌の位置が悪いと、
といった問題も引き起こします。
だからこそ「まだ乳歯だし様子見ようかな」は
お子さんの将来にとって大きなリスクかもしれません。
1歳から始まる大切な口腔ケア —— 「磨かせない子」にさせないために
生後6〜8ヶ月頃に乳歯が生え始めると、いよいよお口のケアがスタートします。
でも多くの親御さんがここでぶつかる壁、それが
「1歳児が歯磨きを嫌がる問題」です。
なぜ1歳の子は歯磨きを嫌がるの?
歯磨きを嫌がらない子に育てる7つのコツ
1️⃣ いきなり歯ブラシでゴシゴシしない
まずは唇や歯茎に優しく触れたり、ガーゼで拭いたりして「お口を触られること」に慣れさせる。
2️⃣ 可愛いキャラクター歯ブラシ・フレーバー歯磨き粉
子どものモチベーション爆上がり。大好きなアンパンマンやしまじろうが大活躍。
3️⃣ 「寝かせ磨き」が鉄則
親が正座して膝を開き、そこに頭を乗せる。動きにくく、親も磨きやすい。
4️⃣ 歌やごっこ遊びで楽しい時間に
「歯磨きのうた」「歯磨きごっこ」で嫌がる時間を楽しいイベントへ。
5️⃣ 歯茎を守るのが大人の仕事
強く磨きすぎない。上唇小帯(上前歯のヒダ)に注意して優しく。
6️⃣ 終わったら思い切り褒める
これで子どもは「褒められるからやる」が刷り込まれる。
7️⃣ 親が楽しそうに磨く姿を見せる
お手本を見せるだけで子どものやる気が変わる。
実は一番怖い「口呼吸」 —— そのまま放っておいて大丈夫?
新潟大学の調査(2021年)では、
なんと31%の子どもが誰から見ても分かる「お口ぽかん」状態、
さらに唇がちょっと開いている「隠れ口呼吸」まで含めると、
約80%が口呼吸だという衝撃的なデータがあります。
これ、自然には治りません。
国も「小児口腔機能発達不全症」という病名を新設し、保険適用まで認めているほど深刻です。
口呼吸が子どもに及ぼす恐ろしい影響
鼻呼吸で人生が変わる
鼻呼吸のメリットは計り知れません。
口呼吸を鼻呼吸に戻すだけで、脳への酸素供給が安定し、集中力や性格、体格にまで良い影響があるのです。
小児矯正(マイオブレイス)で根本から変える
スマイル10矯正歯科・小児歯科が推奨するのは、
単に歯を動かす大人の矯正ではなく、
子どもの成長を活かしながら顎を正しく育てる小児矯正。
その代表格が「マイオブレイス」です。
🌈 マイオブレイスの3本柱
1️⃣ 日中1時間マウスピース装着
これが一番の肝。鼻呼吸に必要な筋肉を強制的に使わせ、習慣化を促します。
2️⃣ 毎日5分のアクティビティトレーニング
動画を見ながら呼吸・舌・唇・頬・嚥下の筋肉を鍛えます。
3️⃣ 夜間も装着して寝る
寝ている間の低位舌を防ぎ、成長ホルモンがしっかり分泌される質の高い睡眠へ。
✅ マイオブレイスのメリット
小児口腔機能発達不全症と国が認めた問題
今、国が本格的に動いているのが「小児口腔機能発達不全症」という問題。
これは、
国が動いた背景には、
“子どもの3人に1人は何らかの発達不全がある”
という深刻なデータがあります。
この状態を放っておくと、
と、将来的に心身の健康・社会性にまで悪影響を及ぼす可能性があります。
家庭でできる!食育&癖改善プログラム
スマイル10矯正歯科・小児歯科では、ただ医院で治療するだけでなく、
「おうちでの毎日の習慣」が何より重要だと考えています。
だからこそ来院されたママパパには、家庭で取り組めるこんなことをお伝えしています👇
🍙 よく噛む食事を意識する
✋ 癖の早期発見&対応
👅 舌のトレーニング
🚰 鼻呼吸を促す
都筑区センター北だから叶う「ママ友ネットワーク」活用
実は横浜市都筑区、特にセンター北エリアは
という特性があります。
だからスマイル10矯正歯科・小児歯科には、
という患者様がとても多いんです。
スマイル10矯正歯科・小児歯科の小児チームの想い
当院はただ「歯をきれいに並べる」ための場所ではありません。
✅ お子さんがしっかり噛んで食べられること
✅ スムーズに呼吸ができ、脳にたっぷり酸素を送れること
✅ 正しい顎の成長で、その子らしい素敵な顔立ちをつくること
✅ コンプレックスなく笑顔でいられる未来をつくること
これが私たちスマイル10矯正歯科・小児歯科の小児チーム全員の願いです。
ママパパの声「ここに来て本当に良かった」
よくある質問Q&A
Q:まだ5歳ですが、相談は早いですか?
➡ いえ、5歳はむしろベストタイミング。上顎骨の成長が活発なこの時期に改善を図ることで、将来の抜歯や長期矯正のリスクを減らせます。
Q:マイオブレイスって痛いですか?
➡ 痛みはほとんどありません。最初は違和感がありますが、日中1時間の練習で徐々に慣れていきます。
Q:費用はどのくらいかかりますか?
➡ ケースによりますが、通常は50万〜60万円程度です。都度払いプランや分割払いも可能なのでご安心ください。
Q:習い事や学校に影響はありませんか?
➡ 日中1時間+夜寝る時に装着なので、学校生活や習い事への影響は最小限です。
センター北でママ友に差をつけるなら、今がチャンス!
子どもの矯正は早ければ早いほど、
と良いことだらけ。
逆に遅れると、
となるリスクが上がります。
当院は小児だけでなく、大人のホワイトニング・セラミック・インプラントも対応しているため、
家族みんなでトータルにサポート可能です。
📞 まずは気軽にカウンセリングを
【監修者紹介】
山口 和巳(やまぐち かずみ)
はじめまして。汐入駅前歯科 総院長の山口和巳です。
私が歯科医師を志したのは、中学3年生のときに父を病気で亡くしたことが大きなきっかけでした。母が一人で私を懸命に育ててくれたことへの感謝とともに、家族を失う悲しみや医療の大切さを強く感じ、この道を目指しました。母の負担を少しでも軽くしたいという思いから、国立の新潟大学歯学部へ進学し、国民の皆様の税金に支えられながら学ばせていただきました。
今こうして歯科医師として働けているのは、学生時代から多くの方々に支えていただいたおかげです。だからこそ、その恩を地域の皆様に少しでもお返ししたいという思いを胸に、日々診療に取り組んでいます。
私のポリシーは「できる限り多くの方に質の高い歯科医療を提供すること」。経営面では決して器用ではありませんが、目の前の患者様に対して損得を一切考えず、「ここに来てよかった」と思っていただける治療を常に心がけています。
私が理想とする医師像は、映画『パッチ・アダムス』に登場する医師のように、人として温かく、誠実に寄り添える存在です。その姿に少しでも近づけるよう、今もさまざまな勉強会やセミナーに参加し、最新の技術を学び続けています。
これからも一人でも多くの方の健康を支えられるよう、技術を磨き、人間としても成長を重ねてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
略歴:
【本院のご案内】
〒238-0041
神奈川県横須賀市本町3丁目27
ベイスクエアよこすか一番館 2
046-820-0811
「汐入駅」から徒歩1分の好立地で診療しています。汐入駅向かいのベイスクエア横須賀一番館横須賀アプト2F(横須賀芸術劇場の下)までお越しください。
2025年7月16日 カテゴリ:Smileブログ and tagged 小児矯正
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。
また以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生局に届出を行い、歯科医療に関わる医療安全について以下の通り取り組んでおります。
・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとに交換し、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な院内感染防止対策を講じています。
感染症患者様に対する歯科診療に対応する体制を確保しています。
歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師を1名以上配置しています。
職員を対象とした院内感染防止対策に係る標準予防策等の院内研修等を実施しています。
見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っています。
年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告しています。
・歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)
偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師を1名以上配置しています。
歯科医師の複数名配置、又は歯科医師と歯科衛生士をそれぞれ1名以上配置しています。
患者様にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な装置・器具等を有しています。また、自動体外式除細動器(AED)については、保有していることがわかる院内掲示を行っています。
当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っています。
歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備しています。
医療安全管理者を設置しており、歯科医療を担当する保険医療機関です。
見やすい場所に、緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っています。
・歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)
歯科医療を担当する保険医療機関です。
歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行なっています。
歯科医師の複数名配置、又は歯科医師を1名以上配置かつ歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けた職員を1名以上配置しています。
院内感染管理者を配置し、院内感染防止対策に係る研修を受けた職員を配置しています。
歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保しています。
・歯科訪問診療料の注15に規定する基準(歯訪診)
直近1ヶ月に歯科訪問診療及び外来で、歯科診療を提供した患者数の割合が95%未満の保険医療機関です。
・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)
当院では、歯科補綴治療に関する専門知識を持ち3年以上の経験を有する歯科医師を1名以上配置しています。歯科用CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計装置を導入し、CAD/CAM冠やCAD/CAMインレーの製作が可能な体制を整えています。
・クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)
当院では装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2 年間の維持管理に取り組んでいます。異常を感じた場合は、早めにご相談ください。また、冠やブリッジが外れてしまった場合は、捨てずにご持参ください。
2025年3月31日 カテゴリ:医院からのお知らせ
こんにちは!
横浜市都筑区 センター北駅から徒歩1分のSMILE10 矯正歯科・小児歯科です!
10月に入り、季節のうえでは秋。日中は過ごしやすくなってきましたね!
朝晩も冷え込むようになってきましたので、体調を崩さない様気を付けましょう!
さて、先日、気になるニュースがありました。
それは、「子どもの歯並びが悪くなっている」というニュースです。
その内容は、子ども達の歯並びを現場で見ている全国の歯科医師約1,000人を対象に、「子どもの歯並びは年々悪くなっていると感じますか?」と質問したそうです。
その結果は驚くべきもので、回答した歯科医師の実に98%が「はい」つまり、「子どもの歯並びが年々悪くなっている」と答えていました。
じつは実際に日々患者(子ども)さんの歯、お口の中を見ている我々が歯科治療の現場で感じている率直な感想でもあります。
皆さんもニュースやコラムなどで見たことがあるかもしれませんが、日本人が食べ物を食べる際、「物を噛む回数」が減り顎が十分に発達していない、と言うようなニュースが一時期流れていたことがありました。
もちろん、これだけが原因では無いのでしょうが、一つの要因ではあります。
子どもの歯並びが悪くなる原因はいくつもあります。子どもの歯並び相談にいらした保護者の方から「遺伝で歯並びが悪くなったのでしょうか?」と、ご質問を頂きます。遺伝も歯並びが悪くなる原因の一つと言われていますが、生活習慣の変化も大きく影響しています。
<歯並びが悪くなる要因>
・柔らかい食べ物が多くなり、咀嚼回数(食べ物を噛む回数)の減少
・成長期の口呼吸
・幼児期の指しゃぶり
歯並びが悪いことはいけないことではありません。ですが、近年の最新研究では、「歯並びが体の発達」にも影響する事が分かっています。
例えば、これは成人の方に多いのですが、歯並びが悪いと歯磨きの時に歯ブラシで磨きにくい箇所ができてしまい、毎日の歯ブラシが適切に行えていないと、「むし歯」や「歯周病」のリスクが増えます。
歯並びが悪い状態が、知らず知らずのうちにむし歯や歯周病に繋がる可能性があり、年を取った際に歯を失ってしまう要因になります。
子どもの場合、歯並びや噛み合わせが悪いと、顎周りの筋肉が発達せず、顔の輪郭にも影響が出る事もあります。
実際に、当院の子ども矯正治療(マイオブレース)を受けて、治療から数カ月~1年ほどすると、歯並びが良くなるだけでなく、「顔の形」が変わり保護者の方も驚く事がよくあります。※治療の進捗や結果には個人差があります。
意外に知られていませんが、子どもの歯並びの影響は顔の形だけでなく、小学校~中学生頃には、スポーツや運動にも影響が出ると言われています。これは歯並びや咬み合わせが悪いため、力を入れる時に歯を食いしばる事が出来ず、運動能力・運殿結果に差が出る事があるそうです。
スポーツをやっているお子さんは、一度歯並びの状態を相談してみるのも良いかと思います。
昔は、「歯並び」の矯正は見た目の美しさという審美的な面が強いイメージがありました。
しかし、近年の最新研究で歯並びが体の発育に影響する事が分かったこともあり、ここ数年は「子どもの健康と健やかな成長」のために、歯並びを治したり歯並びが悪くならないように予防する方がとても増えています。
歯科に関する研究や積み重ねた経験、ノウハウにより、幼児期から定期的にお口の状態を管理することで、歯並びの状態を定期的にチェックして「歯並び」が悪くなる事を事前に予防し、そもそも歯並びが悪くなる原因自体を改善する事ができるようになったのです。
当院でも最新の予防矯正「マイオブレース」を導入しています。
最新の予防矯正マイオブレースでは、子どもに出来るだけ負担が掛からないように、取り外し可能なマウスピースを使い、子どもが楽しくできるアクティビティ、食生活や習慣、食べる物の選び方を専門家がサポートします。
歯並びが悪くなる原因は、呼吸や嚥下(飲み込み)、咬み合わせ、舌の位置などの悪癖と、顎の発達が十分に促されず生えてくる歯が並ぶスペースが無くなることです。
最新の予防矯正マイオブレースでは、歯並びが悪くなる大きな要因をトレーニングで改善していきます。
しっかりとトレーニングを行う事で、歯並びが悪くなる原因自体を取り除きますので、子どもが成長しても後戻りする事がなく、大人になって追加の矯正を行う必要が無くなります。
歯並び矯正というと敷居が高いイメージかもしれませんが、子どもの成長に関わる身近なサポート方法の一つとしてどんどん広がっています。
口呼吸をしていたり上手く食べ物が呑み込めなかったり、子どもの歯並びに問題無いか気になる方はぜひ一度、当院にご相談してみませんか?
専門の教育研修を積んだプロの歯科医師、歯科衛生士が子どもたちが楽しく通えるように全力でサポートいたします!
もちろん、歯並びの改善は子どもだけではありません。大人の方でも遅くはありませんよ!
成人の方にも、最新のマウスピース矯正インビザラインで歯並びを治す事も可能です。
当院が皆さんの歯並びを正確に診断して適切な治療をご提案しますので、お気軽にご相談ください!
2023年10月16日 カテゴリ:Smileブログ
こんにちは!
横浜市都筑区 センター北駅から徒歩1分のSMILE10 矯正歯科・小児歯科です!
毎日猛暑が続きますが、皆様ご体調はいかがでしょうか。
真夏ですので、とにかく熱中症への警戒と予防が重要です。
熱中症への予防には、しっかりと睡眠をとること、水分と塩分の補給、室内にいる際もエアコンを使用する等、
体温調節に気を付けましょう!
特に、ご高齢の方やお子さまは体温調節にくれぐれもお気をつけください!
さて、皆様は「認知症」をご存じの事と思います。
「認知症」は、様々な原因により脳細胞の働きが悪くなってしまい、記憶力や判断力に障害が発生し、日常生活に支障をきたす病気で、「加齢によるもの忘れ」とは違います。
この認知症ですが、日本ではなんと65歳以上の方の5.4人が認知症と言われています。
※平成29年 内閣府調査より
認知症にはアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症・前頭側頭葉変性症等の種類があり、投薬により進行を遅らせる治療がありますが、根本的に病気を治療する治療法は未だ確立されていない病気です。
認知症にも様々な型がありますが、治療法が確立されていない上記の3つの型が、認知症の94%を占めていると言われています。(アルツハイマー型認知症が70%)
病気を治す治療法が確立されていないため、認知症に対する様々な予防法が提唱されています。
そして、最近の研究では認知症の発症には歯周病が関わっている可能性が高い、という事が分かり始めてきました。
認知症は、脳の神経細胞に異常が発生し、自分の行動、身近な人や物の名前が思い出せなくなる記憶障害、判断能力の低下等、日常生活を阻害してしまう病気です。メディアでも認知症を取り上げていますので、皆さんもご存じの方が多いかと思います。
この認知症ですが、先日、九州大学の最新研究で認知症患者の脳内から「歯周病の原因菌」が検出されたとニュースがありました。この研究により、認知症の治療法開発につながるのではないかと注目されています。
これまでも口腔内の細菌が増殖することで全身疾患、体全体にも悪影響があることが分かっていましたが、社会問題にもなっている認知症も「口腔内の環境」が関係している可能性が出てきています。
今回の研究を行った九州大学研究チームからも「正しい歯磨き、定期的な歯医者での検診とクリーニング」を勧めています。
歯周病は国民病の一つで、50歳以上の日本人では約80%が歯周病と言われています。
認知症は、アミロイドベータという異常なたんぱく質が、長年脳に蓄積する事で発症します。
そして、歯周病菌がこのアミロイドベータの脳への蓄積を加速させてしまう事が判明したのです。
また、歯を失うことも認知症になり易いと言われています。
「お口の中を清潔に保つ」ための予防が重要であることは、単にむし歯予防や口臭予防だけでなく、認知症だけでなく、様々な病気の予防にもなり体全体を健康に保つことに繋がります。
では、歯周病を予防するためにはどうすれば良いでしょうか。
それは毎日の歯磨き(セルフケア)と、歯科医院で行うプロフェッショナルケアが重要です。
まず、皆さんが毎日のご自宅で行う歯磨き(セルフケア)ですが、歯ブラシだけでは歯の汚れの6割程度しか除去できません。歯の汚れの残り4割は歯と歯の間や、「歯周ポケット」に残ってしまっています。
ご自宅でのセルフケアでは、歯ブラシと歯間ブラシを使ってケアを行いましょう。
また、歯ブラシや歯間ブラシは様々な種類があり、皆さんのお口の状態によって最適な種類があり、正しい使い方でしっかりとケアする事ができます。
皆さんに合った適切なケアグッズは、当院の歯科衛生士がご提案できますので、お気軽にご相談ください。
お口の予防でもう一つ重要なことは、定期的に歯科医院でプロフェッショナルケアを受けることです。
歯科医院のプロフェッショナルケアでは、毎日のセルフケアでは落としきれない歯の汚れを最新のエアフローで除去し、むし歯やお口のトラブルを早期発見することができ、プロの歯科衛生士が歯磨きの方法等を丁寧にご案内します。
定期的にプロフェッショナルケアを受けることで、将来の健康維持にも繋がりますので、
毎日のセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアをしっかりと行いましょう。
さて、こういった口腔ケアの習慣ですが、お子さまは勿論ですが、大人から始めても遅くはありません。
まずは歯科医院で検診を受け、毎日のセルフケアの方法や自分に合ったケア用品を使うことから始めることで、お口の状態を向上させることができます。
お子さまの場合、できるだけ早めに口腔ケアの習慣を身に付けることが重要です。むし歯予防、歯周病予防だけでなく、定期的に歯科検診を受けることで歯並びのチェックが早めにできます。
なお、新型コロナウィルスの影響で「歯医者に行くのが心配・・・」という方もおられるかと思いますが、当院をはじめ、多くの歯科医院では感染症対策に力をいれています。
医療として歯科は新型コロナウィルスの出現前から、様々な感染症の予防に力を入れてきました。
当院でも新型コロナウィルスを始めとした感染症の予防に力を入れていますので、安心してご来院ください!
歯科医師、歯科衛生士がしっかりと皆さんの口腔ケアをサポートしますので、まずは歯科医院に足を運んでみましょう!
2023年8月28日 カテゴリ:Smileブログ
こんにちは!
センター北駅 徒歩1分のSMILE10 矯正歯科・小児歯科です。
7月も終わりに差し掛かっていますが、気温は連日35℃を超す猛暑ですね!
日中の日差しが強い日は、熱中症対策としてしっかりと水分補給をしていきましょう!
さて、新型コロナウィルス感染症がまた少しずつ広がっているようです。
普段は感染症予防のため、ご自宅で過ごされている方も多くいらっしゃると思います。
マスクを着用する、手洗いをしっかりと行う事が感染予防の方法ですが、感染症予防や感染しても重症化を防ぐには、ウィルスや病気に負けない体の「免疫力」を高める事も重要です。
この「免疫力」とは、体の中に侵入したウィルスや細菌を撃退する、重要な体の防衛システムです。
この免疫力を強化することで、病気に強くなったり、病気に掛かりにくくなります。
では、免疫力を強化するにはどのようにすればよいでしょうか。
免疫力を強化するには、適度な運動、しっかりと睡眠をとること、健康的な食事(発酵食品や野菜)などが
代表としてあげられます。
そして、最近の研究では、「お口の中を健康的に保つ事で、免疫力が強化される」ことが分かってきました。
新型コロナウィルスの登場以来、世界中の研究者が研究を進めており、口腔ケアをしっかりすることが体の免疫力を高める効果があることがわかったのです。
口腔ケアが直接的に新型コロナウィルス感染予防や重症化リスクに関係しているかは研究中の段階ですが、口腔ケアで免疫力を強化することで、インフルエンザへの感染リスクを低下させることは判明しています。
体の免疫力を高めておくことは病気に負けない健康な体を作ることに繋がりますので、様々な感染症や病気に負けないためにも、しっかりと口腔ケアを行う事が重要です。
「口腔ケアが免疫力をアップさせる」と書きましたが、皆さんご存じでしたでしょうか。
人間には、体に害や悪影響を与える微生物やウィルスなどに対して免疫力が働くことで、病気が軽くなったり、病気自体の発症を未然に防ぐ機能が備わっています。病気の発症は、体に害を及ぼす微生物やウィルスと免疫力のバランスが崩れたり傾いたりした時に起こるため、この免疫力を高めておくことが病気を出来るだけ未然に防ぐ効果があるのです。
先に書きました通り、免疫力を高める方法は様々にありますが、その一つが「口腔ケア」なのです。
実はお口の中には様々な細菌(常在細菌)が居ます。この細菌には体を守る細菌もいれば逆に体に悪影響を及ぼす細菌も居ます。お口の中の免疫システムは、この体に悪影響を及ぼす悪い細菌に対してIgAと呼ばれる抗体が駆除するために働きます。ただ、この悪い細菌の数が多すぎるとIgAの働きが間に合わなくなってしまい免疫バランスが崩れてしまいます。そこで、お口の免疫力を高める方法が「口腔ケア」です。
口腔ケアには大きく2種類あります。
皆さんが毎日ご自宅で行っている「セルフケア」。そして、定期的に歯科医院で行う「プロフェッショナルケア」です。
患者様から、「セルフケアとプロフェッショナルケア、どっちが大事?」というご質問を頂くことがありますが、答えは「どちらも大事」です。
ご自宅でのセルフケアは毎日して頂いていると思いますが、念入りに歯磨きをしても、歯ブラシが届かない位置等、どうしても磨き残しが出てしまったり、歯ブラシでは落とせない汚れが付着してしまうことがあります。
そのため、定期的に歯科医院でプロフェッショナルケアを受けてセルフケアでは落とせない汚れを落とし、口腔内の健康状態を良好に維持する事が重要です。
定期的にプロフェッショナルケアを受ける事で、むし歯や歯周病にかかっていないか、もしむし歯や歯周病になっていたとしても、早期に対応できるため歯を失ってしまうような大きなトラブルを予防する事ができます。
SMILE10 矯正歯科・小児歯科のプロフェッショナルケアでは、
超音波洗浄で、歯ブラシでは取り切れない細部の汚れもしっかりと落としてクリーニングし、
最新の口腔ケア機器「エアフロー」で、歯に傷をつけることなく頑固なプラーク(むし歯の原因となる細菌の塊)や着色汚れも落としていきます。
また、専門の教育を受けた歯科衛生士が、皆さんのお口に合ったセルフケアグッズをご提案し、毎日のセルフケアが効果的に行えるサポートを行っています。
悪い細菌はお口の中のプラークに潜んでいます。毎日の歯磨きをしっかりと行い、定期的に歯医者で磨き残しの除去、口腔状況のチェック、効果的なセルフケア方法の習得でしっかりとお口の健康を保っていきましょう!
病気に負けないための体作り、まずは身近な口腔ケアから始めてみませんか?
当院も感染予防対策を徹底していますので安心してご来院ください!
皆様の口腔ケアサポートはもちろん、生まれたばかりのあかちゃんからお年を召された方まで、SMILE10 矯正歯科・小児歯科にお気軽にご相談ください!
2023年7月31日 カテゴリ:Smileブログ
こんにちは!
センター北駅から徒歩1分の歯医者、SMILE10 矯正歯科・小児歯科です!
6月に入って気温が上がり始め、雨も多くなってきましたね!
梅雨も近く、その後はついに夏がやってきます。季節の変わり目は体調を崩し易い時期ですので、
皆様もお体ご自愛ください。
さて、2021年からの新型コロナウィルス感染症による影響で、長らくマスクをつけた生活が当たり前になっていましたが、今年からマスクの着用は個人の自由となりました。
ただ、医療機関や人の集まる場所では、感染予防のためにマスクを着用される方も多くいらっしゃいます。
屋外・屋内でもマスクをすることが当たり前になりましたが、皆さん、マスクをしていると、口の中が乾いたりしませんか?
マスクを着用した状態では、水分補給をしなくなりやすく、唾液を分泌するための刺激も少なくなって、マスクをしていない状態より唾液が少なくなり、口の中が乾きやすくなるようです。
口の中を潤おしているのは「唾液」ですが、この「唾液」、ただ潤しているだけではありません。
実は、お口の中の健康や病気予防に様々な役目をこなす、大事な存在なのです。
個人差や季節によって差がありますが、唾液は健康な成人では一日1~1.5リットルも分泌されると言われています。
唾液には消化酵素が含まれ、食事の際などは歯でかみ砕いた食べ物を消化酵素が消化し易くする役割を担っています。その他にも、「お口の中の粘膜を守る」役割もあります。
お口の中ってヌルヌルしていますよね?
これは唾液の中に「ムチン」という物質が含まれており、このムチンが食べ物を滑らかにして飲み込みやすくしたり、ねばり気を出して、お口の中の粘膜や舌が、食べ物等で傷つかないようにする大事な働きを持っています。
また、唾液は味覚にも影響します。舌にある味覚を感じる為の味蕾(みらい)に、唾液が味の元となる物質を運ぶことで、食べ物の味を感じることができるのですが、唾液が少ない状態だと味が感じにくくなります。
唾液は消化を助けるだけでなく、お口の中の抗菌作用、免疫作用に物凄い力を発揮しているのですね!
唾液はむし歯の予防にも大事な役割を担っています。
普段の食事の後、お口の中にいるプラーク(細菌の塊)が歯を溶かす酸を出します。
これがむし歯の原因となりますが、このプラークが出す酸を中和して歯の再石灰化を行ってくれるのが「唾液」です。
プラークが出す酸の影響で歯のエナメル質からミネラルが溶け出してむし歯になりますが、唾液の中に含まれているリン酸やカルシウムなどのミネラル成分が歯に補給されることで、歯のエナメル質を健康な状態に戻す再石灰化でむし歯を予防してくれます。
唾液の量が減り、歯の再石灰化が進まない、食べ物がしっかりと消化されず、お口の中の自浄作用が低下してむし歯になってしまうのですね。
また、唾液の量が少なくなってしまうと、歯周病の原因になったり、口臭の原因になったりします。
ご高齢の方の場合、入れ歯の適合が悪くなったり嚥下(物を飲み込むこと)障害が起こったりすることもあります。
普段あまり意識する事の無い「唾液」ですが、このように体の健康や大事な味覚、むし歯予防にとても大事な役目を持っているのですね。
さて、この大事な唾液の量を増やすにはどうすればよいでしょうか。
食べ物を良く噛んで食べる事はもちろんですが、会話やガムを噛むことで唾液の量を増やす事はご存じかもしれません。それ以外にも方法があります。
唾液を増やすには、耳の下にある耳下腺を刺激したり、顎の真下を指でグッと押して舌下腺を刺激する事で
唾液が増えます。
もちろん、こまめな水分補給も非常に効果的です。
私たち歯医者でも、患者さんの口腔環境を調べる際に唾液が重要なポイントになっています。
むし歯や歯周病に掛かるリスクは、一人一人違ってきます。基本となる予防はできるのですが、皆さん一人一人にあった方法でむし歯や歯周病を予防する事もとても大事な事です。
唾液を調べる(「唾液検査」)ことで、皆さんのむし歯の原因や、将来起こる可能性がある口腔環境へのリスクを知る事ができます。
唾液検査は、10分~15分程度で、皆さんのお口の中の状態(むし歯菌や酸性度等)を測定し、むし歯や歯周病、口臭のリスクを調べることができます。
この唾液検査の結果により同じ治療や処方だけでなく、皆さん一人一人にあったお口のケア方法や歯磨き粉、ケア用品等をご提案し、患者さん毎に合った対応が出来ることが大きなメリットです。
最近では、小さな子どもの頃から唾液検査を行う事で、将来のむし歯や歯周病を予防するための予防処置やケアを行い、お口の健康に力を入れる親御さんもとても増えています。
今はお口の中の状態に異常やトラブルがなくとも、将来のリスクを知る事でもっと効果的に予防が出来ることが多くなります。
まずは一度、唾液検査やってみませんか?
ご興味がある方はお気軽にご相談くださいね!
2023年6月28日 カテゴリ:Smileブログ

こんにちは、SMILE10 矯正歯科・小児歯科のしまだです。
みなさん、歯医者さんの定期検診には通っていますか?
今回は、定期検診の重要性についてのお話を致します。
どんなことをやっているかもご紹介しておりますので、いつも通っているけど内容が気になる方も、ぜひご覧ください。
 定期検診は、一般的にメンテナンスとも呼ばれています。
定期検診は、一般的にメンテナンスとも呼ばれています。
メンテナンスとは、歯と口の健康を維持するための管理のことです。
歯石やプラークの除去だけでなく、お口の健康が悪くなっていないかも確認しています。
例えば、お口全体の虫歯の検査や、ブラッシング方法のアドバイス、歯周病の検査などを行います。
メンテナンスの期間は、患者さんの歯の状態によって異なりますが、通常は3ヶ月に1回が効果的と考えられています。
歯医者さんに定期的に通うことは、お口の健康を保つために重要なことです。
このブログでは、いくつかの日常的なケアを取り上げていきます。
〇歯肉のチェック
歯周プローブと呼ばれる器具を使って、歯周ポケットの深さをはかります。
健康な歯茎は通常、固くて淡いピンク色をしており、歯の周りにぴったりと収まっています。
歯周病が進んでくると、この歯周病ポケットが深くなっていきます。
〇むし歯のチェック
むし歯は、噛む面だけでなく、歯の根元や直接見えないところにもできます。
そのため、専門的にむし歯のチェックをすることが大切です。
〇ブラッシング指導
虫歯や歯周病を防ぐためには、正しい歯磨きをすることが大切です。
歯科衛生士から直接、正しい歯磨きの方法、歯間ブラシやデンタルフロスなどの使い方を教わる事ができます。
あなたに合ったセルフケアの方法を知る事ができますよ!
また、お子様には染め出しをして、汚れの付きやすい部分を確認することもできます。
〇歯石の除去
歯石は、歯の表面に付着して固まったプラークで、歯周組織の刺激や炎症を引き起こす原因になります。
歯石は自分で取り除くことができないため、歯科衛生士によるクリーニングが必要になります。
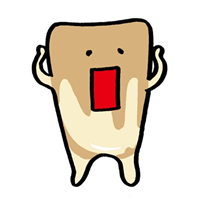
〇お口の中の粘膜や病気のチェック
唇や舌、頬、口角などの粘膜に炎症や変化がないかどうかを確認します。
口腔がんなどの早期発見のためには、お口の粘膜に異常がないか確認することが大切です。
〇歯科相談
●むし歯や歯周病など、お口の健康問題に加え、ホワイトニングなどの審美的な問題についての相談も受け付けています。定期検診は、お口を健康に保つためにとても大切です。
●当院では、衛生士専用のユニットを用意し、リラックスした雰囲気でクリーニングができるようにしています。
また、当院では歯科衛生士担当制を採用しております。
いつも同じ歯科衛生士がお口の状態を確認することで、わずかな状態の変化も見逃さないようにしています。
歯科医師、歯科衛生士で協力して、お口の健康を守っていくことにつながりますし、患者さんにとっても同じ衛生士さんという安心感が得られます。
〇歯周病と全身の健康について
歯周病が全身の病気と関係していることをご存知ですか?
歯周病は、歯の健康だけでなく、全身の健康を脅かすものなのです。
どんな病気が関係しているのか、探って見ましょう。
*心臓病(狭心症、心筋梗塞など)
*糖尿病
*脳血管障害(脳梗塞など)
*動脈硬化
*呼吸器疾患
*早産低体重児
*誤嚥性肺炎
など…
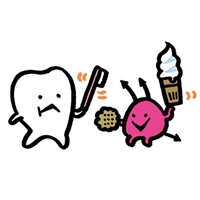
以上のような、さまざまな病気と関連しています。
このように、歯周病の影響は口の中だけにとどまらず、全身に及んでいることが明らかになっています。
●歯周病と糖尿病の関係
歯周病がなぜ糖尿病と関係するのでしょうか。
歯周病になると歯茎が腫れて、出血しやすくなったり、膿が出たりします。
そうすると炎症を起こした歯茎の歯周ポケットから、炎症に関係する化学物質が放出されます。
この化学物質の中には体内のインスリン分泌を阻害するものがあります。
インスリンが減ると血糖値が下がりにくくなるので、糖尿病の発症や悪化のリスクを高めることにつながるのです。

●歯周病と、心臓病や脳血管疾患との関係
歯周病になると歯茎が炎症を起こして腫れて、時には歯ブラシなどで軽く触れただけでも出血します。
その時、血管の中に歯周病の菌が入り込み、血液にのって全身をめぐることになります。
この歯周病菌は血液の流れを妨げるので、血管が詰まりやすくなり、狭心症、心筋梗塞などの心臓病や、脳梗塞などの脳血管疾患になりやすくなります。
歯周病が重度であるほど、歯周病菌は血液に入りやすくなります。
調査によると、歯周病に罹患している人は、歯周病でない人に比べて、心臓病や脳血管疾患のリスクが2.8倍高くなると言われています。
●歯周病と呼吸器疾患、誤嚥性肺炎の関係について
日本人の死亡原因ランキング第3位が何かご存知でしょうか?
それは肺炎です。風邪のせいだと思われがちですが、そうではありません。
75歳以上の要介護者の場合、肺炎は死亡原因の第1位となっています。
肺炎の代表的なものは誤嚥性肺炎です。
誤嚥性肺炎は、食べ物を飲み込んだ時に誤って器官に食べ物が入ってしまうことから始まります。
その時に、歯周病菌の混ざった食物や唾液も一緒に肺に入ってしまうことで感染し、命にかかわる病気にまでつながります。

誤嚥性肺炎は、お口の中の歯周病菌の濃度が高いほど発症の可能性が高くなります。
誤って気管に入ったものは、反射的に咳で吐き出すのが理想的ですが、筋力が低下していると吐き出すのが難しく、誤嚥性肺炎を引き起こすことがあります。
お口の中を清潔に保っていれば、歯周病菌の濃度が減り、リスクを抑える事ができます。
誤嚥性肺炎の予防には、継続的な歯科検診はとても大切です。
●歯周病と早期低体重児出産(早産)の関係
早産や胎児の発育不全の原因に、羊水や羊膜の感染が挙げられています。
正常に出産をした際の子宮内汚染率は1%未満であり、子宮内に細菌感染を起こすと、早産や低体重児出産の危険性があること示しています。
妊娠初期には個人差があるとはいえ、つわりなどで全体的なブラッシングが難しくなる方もいらっしゃいます。
そんな時は、歯磨き粉をつけないでブラッシングをしてみてください。歯磨き粉の味やにおいで気分が悪くなってしまうのであれば、無理に使う必要はありません。
また、歯ブラシだけでも気分が悪くなってしまう場合は、うがい薬を使って、よくお口をゆすぐだけでも効果があります。
このように、歯肉疾患は口腔内だけでなく、全身の病気と関係していることがわかります。
定期的な歯科検診を受けることは非常に重要です。
〇歯周病と認知症の関係について
歯周病が全身疾患に関わる事は先ほどお伝えさせて頂きました。
歯周病が認知症のリスクも上げてしまう事はご存知でしたでしょうか?
歯周病菌は、血流にのって脳内に侵入し、認知症になる可能性を高めることが分かっています。
歯周病によって歯茎に炎症が起きると、血液に炎症物質であるサイトカインが入ります。
サイトカインはアミロイドβという「脳のゴミ」と呼ばれるタンパク質を増やしてしまいます。
サイトカインは記憶を司る海馬に蓄積されて脳を少しずつ圧迫し、脳の細胞を死滅させてしまいます。脳細胞が減っていくことで少しずつ記憶力が低下していきます。
このように歯周病は、認知症の中で最も大きな割合を占めるアルツハイマー病の発症や悪化の要因になる可能性があります。

さらに、歯周病は歯が抜ける一番の原因でもあります。
歯がないと咀嚼ができませんし、咀嚼は脳への大切な刺激になります。
この刺激が脳に運ばれないと、脳の機能が低下し、認知症になる可能性が高くなると言われています。
●認知症の症状について
認知症になると、脳機能が低下によるいろいろな症状が現れます。
➀記憶障害 記憶を忘れてしまう
➁判断障害 理解力が低下し、判断や、新しいことを理解できなくなる
③見当識障害 人の顔、今いる場所や時間が分からなくなる
④実行機能障害 慣れていることでも出来なくなる など…
また、日常生活を送ることが困難になり、多動、イライラ、排泄困難、不規則な食事、昼夜逆転、幻覚、妄想、徘徊などの症状が現れることもあります。
これらの症状は環境によって引き起こされることが多いため、環境を変えることでリラックスし、改善する場合もあります。
また認知症の進行が進むと、専門家によるサポートや介護が必要になることがあります。
介護は行う側の負担も大きく、介護うつ、介護疲れがよく問題になります。
介護者のうつ病の兆候としては、食欲不振、睡眠障害、疲労困憊、不安感、心理的苦痛などが挙げられます。
また2025年には、高齢者人口の5%が認知症になると予測されています。
認知症になる確率は年齢が上がるにつれて高くなります。したがって、認知症は誰もがかかる可能性があると考えるのが妥当でしょう。
しかし、幸いなことにアルツハイマー病は今から予防することが可能です。
お口の中を綺麗にしておくことで、効果的に認知症を予防しましょう!

歯周病は、認知症・物忘れだけでなく、糖尿病、脳血管障害、肺炎など、さまざまな病気の引き金になったり、悪化させたりする原因にもなります。
これらの病気を防いでこれから健康に過ごしていくために、ぜひ定期検診をご受診ください!
私たち歯科衛生士が、これから先の健康維持をサポートさせていただきます。
2023年4月18日 カテゴリ:Smileブログ